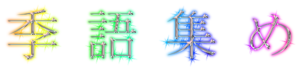大 寒
【鑑 賞】 大寒の水をうましとひとり言
昭和初期から平成初期にかけての俳人・細見綾子(ほそみあやこ)の作品。
大寒の水に対する特別な思いが伝わってくる句。
この句の趣向と似たものが感じられる俳句作品には、鈴木真砂女(すずきまさじょ)の次のような句があります。
ふるさとの大寒の水甘かりき
以下、季語「大寒」の解説です。
【表 記】
(漢字) 大寒
(ひらがな) だいかん
(ローマ字) daikan
【季 節】
冬
【分 類】
時候
【意味・説明】
大寒とは、一年を24等分したものに季節の名前を付けた二十四節気の一つです。
大寒の日付は毎年 1月20日頃となります。
1/20 ~ 2/3頃の期間を「小寒」ということもあります。
【例 句】
※ 有名俳人の俳句を中心に集めました。
一輪にして大寒の椿朽つ
(皆吉爽雨)
薄日さし荒野荒海大寒なり
(福田蓼汀)
消し加ふ大寒の稿繰返し
(大野林火)
しばざくら大寒一花庭ももいろ
(山口青邨)
大寒と云顔もあり雛たち
(小林一茶)
大寒と敵のごとく対ひたり
(富安風生)
大寒ときくや時計のネヂ巻きつゝ
(細見綾子)
大寒に入る日毎年初大師
(星野立子)
大寒の赤子動かぬ家の中
(飯田龍太)
大寒の入日野の池を見失ふ
(水原秋桜子)
大寒の終りを澄める雲に禽
(飯田龍太)
大寒の鏡影のみよぎりたり
(桂信子)
大寒の木々にうごかぬ月日あり
(桂信子)
大寒のここはなんにも置かぬ部屋
(桂信子)
大寒の紙縒一本座右にとる
(皆吉爽雨)
大寒の稀有の暖雨と入りにけり
(石塚友二)
大寒の古りし手鏡冴えにけり
(桂信子)
大寒の底光りせる樫青葉
(高澤良一)
大寒の空の白壁日もすがら
(阿部みどり女)
大寒のただ中にある身の廻り
(富安風生)
大寒のたましひ光る猫通す
(斎藤玄)
大寒の展開するを見守らむ
(相生垣瓜人)
大寒の鍋ぴかぴかと磨きあげ
(鈴木真砂女)
大寒の日輪一語放たるる
(柴田白葉女)
大寒のぬくき日向をひろひゆく
(高木晴子)
大寒の橋一つある通夜の道
(岸田稚魚)
大寒の日は金粉のごとく降る
(山口青邨)
大寒の埃の如く人死ぬる
(高浜虚子)
大寒の星とぼしらに清しかり
(上村占魚)
大寒の星に雪吊り光りけり
(久保田万太郎)
大寒の星みな高くかたまれる
(岸風三楼)
大寒の鵙舌打つてかなします
(岸田稚魚)
大寒のゆるぎなき空日渡る
(上村占魚)
大寒の夜明雪嶺微笑せり
(相馬遷子)
大寒の夜あそびぐせや栄のごと
(草間時彦)
大寒や家のまはりの溝澄みて
(桂信子)
大寒や君が負ひたる太柱
(加藤秋邨)
大寒や転びて諸手つく悲しさ
(西東三鬼)
大寒やしづかにけむる茶碗蒸
(日野草城)
大寒や畳造りの錐を挿し
(山口誓子)
大寒や火の燃えてゐる道の上
(日野草城)
大寒や美事な雨をちりばめて
(原石鼎)
大寒や水あげて澄む茎の桶
(村上鬼域)
大寒をただおろおろと母すごす
(大野林火)
何たること大寒の酒切らすとは
(高澤良一)
働いてゐて大寒もまたたく間
(鈴木真砂女)
人恋しき大寒の夜を訪はれけり
(長谷川かな女)
ふるさとの大寒の水甘かりき
(鈴木真砂女)
万葉に通ず大寒の生姜の香
(長谷川かな女)
双肌に大寒の水あまりけり
(齋藤玄)
【関連季語・子季語】
【他の季語を探す】
◇ 春の季語
◇ 夏の季語
◇ 秋の季語
◇ 冬の季語
◇ 新年の季語
◆ 五十音で探す