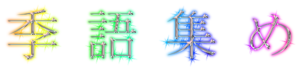雹
【鑑 賞】 暁の雹をさそふやほとゝぎす
江戸時代前期の俳諧師・榎本其角(えのもときかく)の作品。
松尾芭蕉(まつおばしょう)の高弟の名に相応しい句。
また、酒を好み口語調の洒落風を起こした其角らしさが感じられるのは次の句。
暁の反吐は隣か時鳥
あの声で蜥蜴食らうか時鳥
「暁」と「ほととぎす」が詠み込まれた俳句作品を、いくつか味わってみて下さい。
暁のさくらを見たり子規
(柳川琴風)
あかつきの水に残る灯ほととぎす
(鷲谷七菜子)
暁の遊女が吐血ほととぎす
(黒柳召波)
あかつきや地震の後の杜鵑
(高井几董)
時鳥暁傘を買せけり
(榎本其角)
ほととぎす暁の闇紺青に
(橋本多佳子)
落城の暁寒し時鳥
(正岡子規)
以下、季語「雹」の解説です。
【表 記】
(漢字) 雹
(ひらがな) ひょう
(ローマ字) hyo
【季 節】
夏
【分 類】
天文
【意味・説明】
雹(ひょう)は、雲から降ってくる氷の粒のことです。
雹が降ることを「降雹(こうひょう)」、雹による被害を「雹害(ひょうがい)」といいます。
世界的な雹害としては、1888年にインドのムラーダーバードでオレンジほどの大きさの雹が降り 230人が死亡、 1986年にバングラデシュのゴパルガンジで約 1 kgの雹が降り 92人が死亡した例などがあります。
雹は夏に発生することが多く、粒の小さいものは「霰(あられ)」と呼ばれます。
「雹」の語源に関しては、「氷」の字の発音の「ひょう」とする説、「氷雨(ひょうう)」が変化したものとする説など、いくつかの説があります。
単なる「雹」は夏の季語ですが、「春の雹」とした場合には春の季語となります。
【俳句例】
※ 有名俳人の俳句を中心に集めました。
紫陽花にたばしる雹や雨の中
(西島麦南)
葛城の神雹降らす桜かな
(野村喜舟)
君はいま大粒の雹、君を抱く
(坪内稔典)
口中一顆の雹を啄み火の鳥や
(三橋鷹女)
三鬼忌の雹の水輪の大粒に
(石田波郷)
霜と雹たくらむ天に茶の芽立つ
(百合山羽公)
十二階段 辻り落つ雹の頸飾り
(三橋鷹女)
常住の世の昏みけり雹が降る
(中村草田男)
月欠けて野川を照らす雹のあと
(堀口星眠)
天よりの大粒の雹宝珠型
(山口誓子)
鍋もとはしんがり急ぎ雹叩く
(福田蓼汀)
日輪にさわりなき雹止みにけり
(萩原麦草)
雹去るといふ忽ちに梅が香や
(永井龍男)
雹しばし主客の話またもとに
(河野静雲)
雹にうたれ白さも白し大桜
(長谷川かな女)
雹のあと蘂真青に梅こぼれ
(水原秋櫻子)
雹の音こころに昏く麦ありぬ
(臼田亞浪)
雹晴れて豁然とある山河かな
(村上鬼城)
雹降つてしばらく榧の匂ひけり
(古舘曹人)
雹降って天立ち直る穂麦かな
(百合山羽公)
雹ふりし口のかぐはしさ歩きけり
(萩原麦草)
雹降りし桑の信濃に入りにけり
(吉岡禅寺洞)
雹降るや冽々として花の色
(野村喜舟)
雹やみし甘藍畠の日照雨
(西島麦南)
不幸とは五月の雹のごとくくる
(平井照敏)
二つ三つとびたる雹や秋夕立
(高野素十)
山ちかく山の雹降る石の音
(三橋敏雄)
山百合に雹を降らすは天狗かな
(渡辺水巴)
烈日やころげし雹に草の影
(原石鼎)
わが旅の山河あらあらし雹も降る
(山口青邨)
【関連季語・子季語】
春の雹
【他の季語を探す】
◇ 春の季語
◇ 夏の季語
◇ 秋の季語
◇ 冬の季語
◇ 新年の季語
◆ 五十音で探す