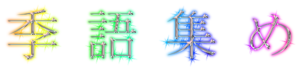雉
【鑑 賞】 雉子鳴くや都にある子思ふとき
明治中期から昭和前期にかけての俳人・杉田久女(すぎたひさじょ)の作品。
子を思う親の切なさが強く感じられる句。
この句と似た趣向が感じられる俳句作品には、次のようなものがあります。
思ひ子をしかるに似たり雉子の声 (三上千那)
子をおもふ声とやけはし夜の雉子 (松岡青蘿)
以下、季語「雉」の解説です。
【表 記】
(漢字) 雉・雉子
(ひらがな) きじ、きぎす、きぎし
(ローマ字) kiji , kigisu , kigishi
【季 節】
春
【分 類】
動物
【意味・説明】
雉(きじ)は日本の国鳥で、雉子(きぎす、きぎし)ともいいます。
雉の鳴き声は「けん」や「ほろろ(羽を打つ音ともされる)」などと形容されます。
なお、「けんもほろろ」は、人の相談などを無愛想に拒絶するさま、取りつくすべもないさまのことをいいます。
【俳句例】
※ 有名俳人の俳句を中心に集めました。
あした鳴き夕べ雉子鳴き住みつかぬ
(加藤秋邨)
ありありと何に畳むるや朝雉子は
(細見綾子)
いくたびも雉子の声するゆあみかな
(百合山羽公)
石段をよぎる雉子あり高山寺
(野村泊月)
宇治川をばたばたわたる雉のあり
(阿波野青畝)
うつくしき男もちたる雉子かな
(炭太祇)
うつくしき顔かく雉子の距かな
(榎本其角)
おきものゝ雉子うつくしや冬ごもり
(百合山羽公)
檻の雉男女手を交しよぎり行く
(瀧井孝作)
隠すべき事もあれなり雉の声
(加賀千代女)
かさこそと雉子落葉に餌をあさる
(寺田寅彦)
元日の墓所の遠くを雉子翔ぶ
(飯田龍太)
雉子うちてもどる家路の日は高し
(与謝蕪村)
久遠寺へ閑な渡しや雉子の声
(飯田蛇笏)
草山に顔おし入れて雉子のなく
(小林一茶)
くれなゐや夕日もへたつ雉子の声
(立花北枝)
刻々と雉子歩むただ青の中
(中村草田男)
兀山や何にかくれてきじのこゑ
(与謝蕪村)
こよひこそ嬉しそうなり雉の声
(正岡子規)
佐保姫の裾にかくるゝ雉子
(松瀬青々)
四五寸の葎に雉の見えずなりぬ
(正岡子規)
滝つぼもひしげと雉のほろゝかな
(向井去来)
たびびとを愕かせたる雉子のこゑ
(松村蒼石)
ちゝはゝのしきりにこひし雉の声
(松尾芭蕉)
吊したる雉子に遅き日脚かな
(石井露月)
つんぼうの耳に地震や雉子の声
(内藤丈草)
寺の湯に音つつしめば雉子鳴けり
(大野林火)
ともすれば十夜の雉子の手を合せ
(松本たかし)
トンネルを出し汽車雉子を飛び立たす
(右城暮石)
拝観の御苑雉子啼きどよもせり
(高浜虚子)
初夢の雉子夕日の山に消ゆ
(飯田龍太)
はりつめし親の心や雉の声
(正岡子規)
はるかにも秘苑の雉子の聞えけり
(鈴木花蓑)
春暮るる雉子の頬の真紅
(福田蓼汀)
春の日の山峡の家雉飼へり
(柴田白葉女)
人うとし雉子をとがむる犬の声
(榎本其角)
ひと声は幻ならず朝の雉子
(石塚友二)
人去つて雉子鳴くこだま瀧の前
(飯田蛇笏)
分別を崩して鳴くや雉子の声
(立花北枝)
わが母の古き命日雉子鳴く
(山口青邨)
【和歌・短歌に詠まれた「雉」】
春の野に
あさる雉の妻恋ひに
おのがあたりを人に知れつつ
(大伴家持)
もえ出づる
若菜あさるときこゆなり
きぎす鳴く野の春の曙
(西行)
立つ雉の
なるる野原もかすみつつ
子をおもふみちや春まどふらむ
(藤原定家)
むさし野の
雉子やいかに子を思う
けぶりのやみに声まどうなり
(後鳥羽院)
をのがつま
こひわびにけり春の野に
あさるきぎすのあさなあさななく
(源実朝)
つつじ咲く
岡の松原松芽立ち
おくの沢辺にきぎすたかなく
(伊藤左千夫)
ところどころ
つつじ花咲く小松原
岡の日向にきぎす居る見ゆ
(正岡子規)
やまたづむ
むかひの森にさぬつどり
雉子啼きとよむ聲のかなしさ
(斎藤茂吉)
月の夜の
ましろき躑躅くぐりくぐり
雉子ひそみたりしだり尾を曳き
(北原白秋)
あからひく
朝靄はるる土手の上に
雉子光りて見えにけるかも
(古泉千樫)
【関連季語・子季語】
雉笛 雉酒
【他の季語を探す】
◇ 春の季語
◇ 夏の季語
◇ 秋の季語
◇ 冬の季語
◇ 新年の季語
◆ 五十音で探す