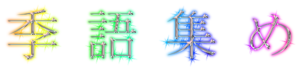どんど
【鑑 賞】 傘の柄にどんど明りと雪明り
大正前期から昭和後期にかけての俳人・阿部みどり女(あべみどりじょ)の作品。
「どんど明り」と「雪明り」の言葉の響きが心地よい句。
「どんど」と「雪」が詠み込まれた俳句作品を、いくつか味わってみて下さい。
とんどして雪汚しゝが清かりき
(細見綾子)
どんど焚くどんどと雪の降りにけり
(小林一茶)
どんど火に雪片狂ひそめにけり
(行方克己)
どんど火のうしろ雪降る夜の川
(只野柯舟)
雪の上をころげどんどの火屑かな
(岸田稚魚)
以下、季語「どんど」の解説です。
【表 記】
(漢字) 歳徳
(ひらがな) どんど
(ローマ字) dondo
【季 節】
新年
【分 類】
人事
【意味・説明】
「どんど」は江戸時代から行われていた行事で、正月に飾った門松・注連飾り、書初めなどを集めて 1月15日に神社などで焚きます。
この火で焼いた団子や餅を食べると無病息災となり、書初めの灰が高く上がると字が上達するといわれています。
地域によって、「どんど、どんど焼き」「とんど、とんど焼き」「どんどん焼き」など、様々な呼ばれ方をしていて、「左義長(さぎちょう)」ともいわれることもあります。
【俳句例】
※ 有名俳人の俳句を中心に集めました。
いくさ知らぬ子らへよぢれてどんどの火
(熊谷愛子)
一切の崩れて終るどんど焼
(池田秀水)
おどろかすどんどの音や夕山辺
(松岡青蘿)
岳麓の石田やよべはどんど焚
(百合山羽公)
火中なる達磨どんどの火を怒る
(岸風三楼)
枯菊にどんどの灰のかゝりけり
(正岡子規)
川風の逆撫でしたるどんどかな
(行方克己)
くろこげの餅見失ふどんどかな
(室生犀星)
小雨降るとんども例の火影かな
(上島鬼貫)
これしきの雨ものかはととんど燃ゆ
(高澤良一)
坂下の屋根明けてゆくどんどかな
(室生犀星)
竹鳴るは節破る音どんど焼き
(高澤良一)
妻の手のどんどの神籤火に投ず
(古舘曹人)
どんど焚く海明けくるを待ちきれず
(岸風三楼)
どんど焚海道沿ひの村ならず
(百合山羽公)
どんど焚その奥に曾我物語
(百合山羽公)
どんど焚く中でも松の爆ぜる音
(高澤良一)
どんどとて道祖神にも米と酒
(福田蓼汀)
どんどの火蜑は舟焼く火となせり
(下村ひろし)
とんど火のあやふく立つてをりにけり
(高澤良一)
どんどの火海へこぼるる母の郷
(鍵和田秞子)
どんどの火衰へ瀬音の高まり来
(阿部みどり女)
どんど火の崩さる音の火中より
(菖蒲あや)
とんど火の最初パチパチやがてバン
(高澤良一)
どんど火の猛る川の面流れをり
(行方克己)
とんどの火たたらを踏んで渚まで
(岸田稚魚)
どんど火の力抜くこと許されず
(菖蒲あや)
どんど火に焙る太腰よき子産め
(岸風三楼)
どんど火に手が花びらの子どもたち
(能村登四郎)
どんど火の崩さる音の火中より
(菖蒲あや)
どんど焼いま完壁の火の柱
(能村登四郎)
とんど焼き海際に大崩れせり
(細見綾子)
どんど焼果てて雪嶺に囲まるる
(石原八束)
どんどより雀の散りし山河かな
(古舘曹人)
波の穂に襲ひかかりしとんどかな
(岸田稚魚)
春の水どんどの灰にぬるみけり
(正岡子規)
ふるさとのどんどの闇の夜見ヶ浜
(木村蕪城)
山神にどんど揚げたり谷は闇
(長谷川かな女)
山川の砂焦したるどんどかな
(芝不器男)
ゆさゆさと海女引いてきしどんど竹
(皆川盤水)
【関連季語・子季語】
【他の季語を探す】
◇ 春の季語
◇ 夏の季語
◇ 秋の季語
◇ 冬の季語
◇ 新年の季語
◆ 五十音で探す